みなさん、おはこんばんにちは。
7月中旬、いよいよ夏本番を迎える今日この頃、みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
筆者は、5月に新たな職場へ転職、全く知らない業界でのスタートから徐々に新しい仕事にも慣れ、ブログを執筆する時間、子供と遊ぶ時間とか、自分のペースで確保できるようになってきました。
自分の理想の生き方、これからも追求していきたいと思います。
ということで? 今回は夏本番、これから夏休みを迎える学生が直面する”あれ”について、大人になって改めて必要性を考えてみました。それを、社会人の目線で書いていきます。
”あれ”とは? そう、夏休みの宿題の鉄板「読書感想文」
きっと学生の時に、こんな風に感じていた人がいると思います。
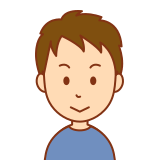
・読書感想文って、読んだ本の感想を書くだけでしょ?意味なくない?
・読書感想文なんて適当に出しても大丈夫でしょ..!
・本なんて全然読んだことない…。
ちなみに筆者自身は、学生時代に読書感想文をまともに書いたことはありません。
そんな読書感想文から逃げてきた筆者が30歳になって気がついたことを元に、”読書感想文に取り組むことへの意義”をつらつらと綴っていきます。
(注意!)
今回お伝えする内容は、”読書感想文の書き方のお勧め” とか”読書感想文におすすめの本、◯選”といった内容では一切ないので、まずご理解ください。
大人になって気づいたこと
自衛隊のエスカレーターな進路から一変、30歳になって初めて真剣に就職活動をした時に、気がついたことがあります。(外資系生保の”P社”の入社面接で気付かされた部分が大きいですが…。)
30歳になって気がついたこと
① 自分/相手の話の要点をまとめられない
② 口頭表現力が乏しい
③ 質問の意図(真意)が読めない
ところで、皆さんはこんな経験はありませんか?
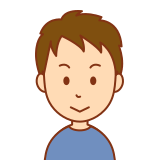
・上司に何かを説明する時に”わかりにくい”とか”説明が長い”と言われる。
・楽しかった思い出を誰かに話しても全然伝わらない。
・相手の質問に対して、的外れな受け答えをしてしまう。
実は「読書感想文」という課題には、仕事ができるビジネスマン/ウーマンになるための必須トレーニング項目がふんだんに含まれているのです。
(※そもそも教育機関である学校が、「なぜ読書した感想を文にさせるのか?」これを考える必要があります。)
筆者は、読書感想文には大きく3つの意義があると思います。
読書感想文の意義①「要約力、要点把握力を身に付ける」
この”要約力、要点把握力”は、コミュニケーションを上手にとるためには必須の能力です。
この能力がある人は、
① 自分の頭の中ので思い描いていることを、わかりやすく相手に伝えることができる。
② 相手の長い話をちゃんと理解できる。
③ 質問に的確に答えることができる。
基本的に読書感想文では、「本の要点を書いた上で、それを読んだ自分の感想を、定められた文字数の中で伝える」ことが求められています。
人に物事を説明する時は、”いかに少ない文字数で、相手に最大限理解させること”を意識すると、伝えたい内容がより相手に伝わるようになります。(逆に文が長くなれば長くなるほど、言葉は”希釈”され、「つまり何が言いたいの?」と相手に思われてしまいます。)
読書感想文は、『本の内容の要点を把握』→『読み手にわかるように本の内容と自分の考え(感想)を要約』→ … この繰り返しです。
文章の要点把握、要約を繰り返し練習できる最高の要約力、要点把握力トレーニングなのです。
(これを第3者がしっかりと添削してあげることで、より要約力に磨きがかかると思います。)
読書感想文の意義② 「文章表現力を深める」
これは少し応用編になります。
本当に優れた文章は、読むだけでその場の情景、色、登場人物の仕草、空気感…etc を読者が勝手にイメージし、あたかもその場に存在しているかのような感覚を読者に体験させるものだと思います。
物事を他人に説明する際に、相手がその情報をビジュアル化(絵に浮かぶ)させることができると、お互いの認識は近づき、認識の齟齬や、相手の勘違い・思い違いは起きにくくなると言われています。
(仕事においては無駄な言葉のやり取りが減ることで業務の効率化を図ることができる上、プライベートでも「この人の話は面白いな」と感じてもらえる確率が上がり、友好関係も広がりやすくなるでしょう。)
なので、”言葉の表現力を磨く”ことは、人間としての魅力を磨くことに直結します。
例えば、とある物語のあらすじを説明する2つの文章があったとします。
例①:その物語は、ある薬で小学生の体になってしまった元高校生の主人公が、難事件を解決していく物語。
例②:大人顔負けの推理力をもつ頭脳明晰な小学生、実はその正体は”名探偵”で全国に名を馳せた高校生名探偵。夜の遊園地で闇の組織の取引を目撃し、口封じのために毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい、小学生の体になってしまった主人公。”高校生名探偵”の存在を闇の組織から隠すため、推理力のちょっぴり冴えない探偵とその娘がいる探偵事務所に居候しつつ、闇の組織の動向や縮んだ体を元に戻す術を探っていく。小学生の体になっても卓越した推理力は衰えず、探偵の陰で腕時計型麻酔銃などガジェットを使い、数々の難事件を解決していく物語。
文章の長さの差こそあれ、どちらの文章で物語が絵に浮かびましたでしょうか?
文字数の定めがある読書感想文では、取り入れるのに限りがありますが、読書感想文を読んだ人に、「何この本?読んでみたい!」と思わせることができたら文章表現力が身についている証、今度はその表現力を口頭で出せるように実践してみましょう。
それができれば、あなたのコミュニケーション能力は他の人より頭ひとつ抜けているはずです。
読書感想文の意義③ 「本を読む習慣・忍耐力を身につけさせる」
最後に根本的な話になりますが、読書感想文に毎年丁寧に取り組むことでこれまでお伝えしてきた「要約力・要点把握力」と「文章表現力」は確実に磨かれます。
ただ、所詮は年に1度の宿題
習慣的に本を読み、自分磨きをしている人には到底敵いません。
なので、現状本を読む習慣が身についていない方は、まず自分のレベルに見合った本を2、3回繰り返し読むことをおすすめします。
きっと1回読んだだけでは気が付かなかったところに気づいたりと物語の深さ、面白さをより知ることができます。) →面白くないことは継続できませんからね
ちなみに、これは大学まで読書に全く縁がなかった筆者が本を読む習慣を身につけた方法になります。
読書の習慣は、勉強や仕事での集中力に活かすことができ、将来的な成功へと繋がる可能性を広げることができると思います。
まとめ
ここまでつらつらと読書感想文の3つの意義について筆者の独断と偏見をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
30歳になって気がついて、自分の学生時代を少々後悔しましたが、今ではそこに気がつけてよかったなと思っています。
30年間の習慣や、積み上げてきたものを今から変えていくのは非常に難しいですが、地道に「人としての魅力」を磨けるように、読書は続けていきたいと思います。
今回はこんな感じで終わります。
以上、解散!



コメント